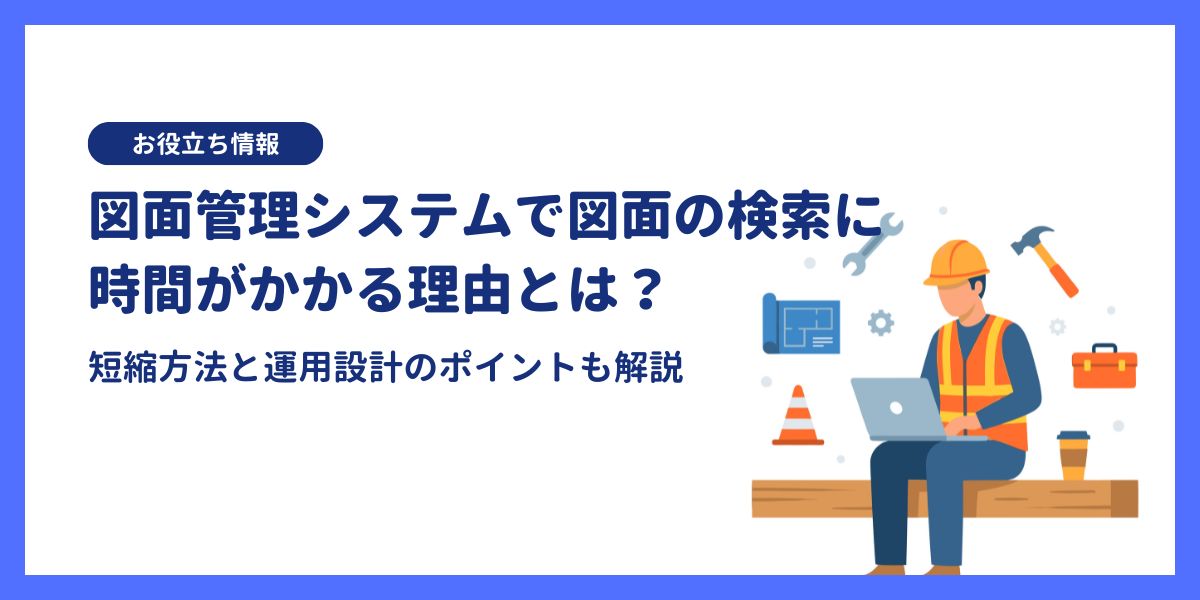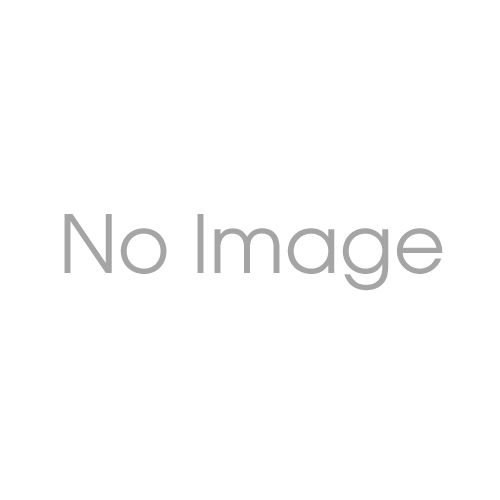紙図面の保管方法とは?図面管理システムを併用するメリットも紹介
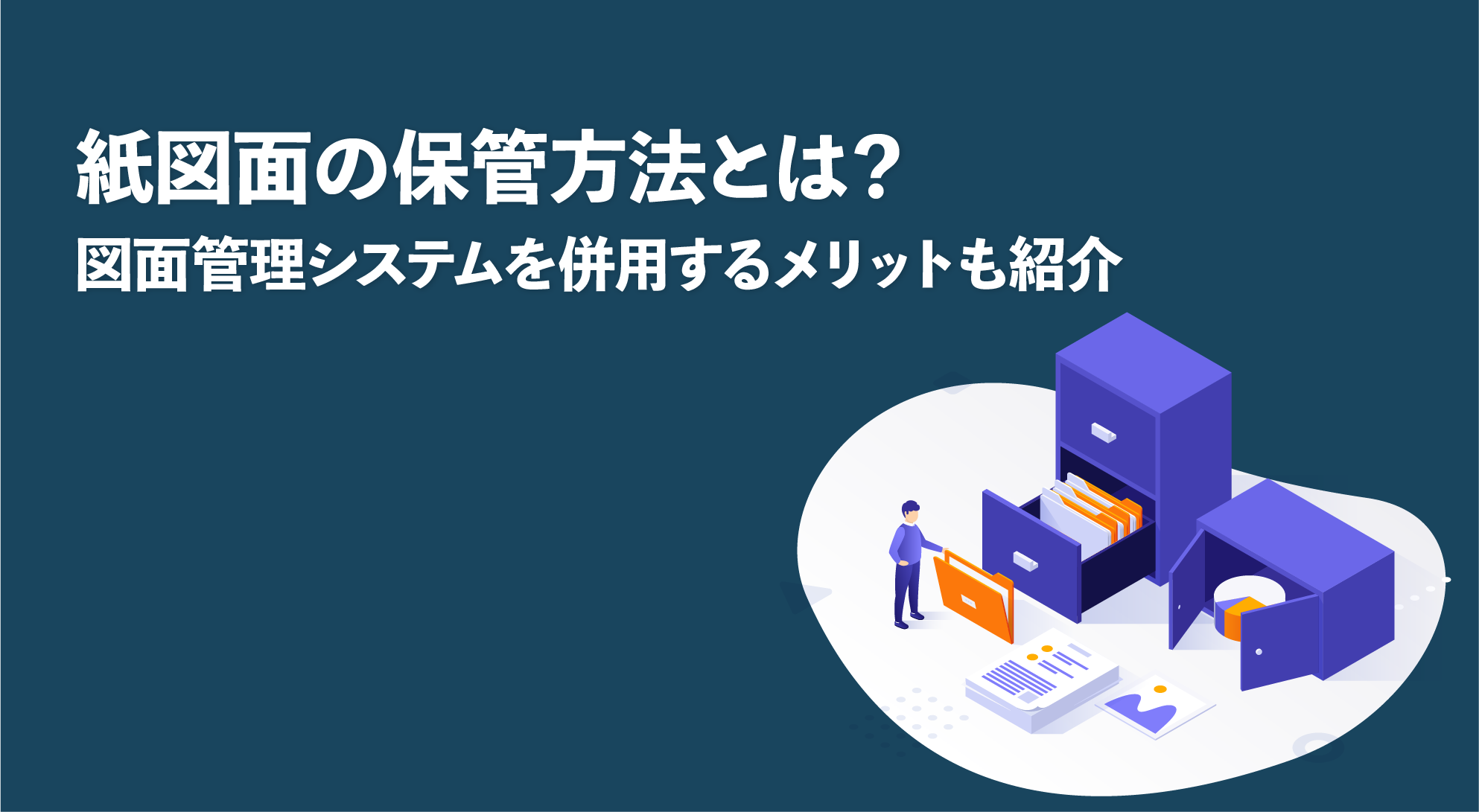
紙図面は直接書き込めたり、パソコンに投影するより全体像を把握しやすかったり、広げて複数人で議論しやすかったりなど利点はあります。一方、紙管理にのみ頼っている場合、「必要な図面がすぐに見つからない」「最新版かどうか確認に時間がかかる」などの課題を抱えているケースが少なくありません。
この記事では、効率的な紙図面の保管方法と、図面管理システムを併用することで得られるメリットを解説します。製造業で図面に携わる方は、参考にしてください。
目次
1.紙図面を保管しなければならない2つの理由

紙図面は法律や業務上の観点から長期保管が必要です。その理由を以下2つ説明します。
- 製造物責任法(PL法)で定められている
- 紙図面は10年間の保管が望ましい
なお、製造業の図面の保管期間と重要性を詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
1-1.製造物責任法(PL法)で定められている
PL(製造物責任)法は、製品の欠陥が原因で、利用者の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者が賠償責任を負うことを定めた法律です。万一のトラブルの際は、設計図や仕様書、試験記録などの関連資料を基に、原因究明や説明責任を果たさなければなりません。
PL法自体は図面の保管義務を直接定めていませんが、記録がなければ対応が困難です。そのため、適切な保管が求められます。
1-2.紙図面は10年間の保管が望ましい
PL法では損害賠償を請求できる期間が、製品の引き渡しから原則10年とされています。そのため、原因究明や説明のために、図面は10年間保管するのがよいでしょう。
なお、海外展開している場合は、各国の規定や運用も確認してください。
2.紙図面の保管の5つの課題

紙の図面は扱いやすい一方、保管には課題が残ります。ここでは、おもな課題を5つ説明します。
- 劣化する
- 紛失する
- 保管場所を確保できない
- セキュリティを担保できない
- 管理しづらい
それぞれ見ていきましょう。
2-1.劣化する
紙の図面は時間とともに確実に傷みます。高温多湿はカビや波打ちを招き、乾燥しすぎると紙が脆くなります。さらに、直射日光や紫外線で線や文字が薄れ、折り目やクリップ跡は破れの原因になることも。
結果として寸法が読みにくくなり、作業ミスのリスクが高まるでしょう。
2-2.紛失する
紙の図面は、人の手を介すため紛失しやすくなります。たとえば、持ち出し後の置き忘れや誤ったファイリング、災害などでの紛失などが起こりがちです。
また、いったん失うと復元が難しく、改訂履歴の追跡や監査対応が滞り、品質や納期にも影響します。
2-3.保管場所を確保できない
紙図面は増える一方で、物理的なスペースを必要とします。とくに大判図面は棚やキャビネットの場所を取ります。結果として、社内スペースが足りず、追加の保管庫や外部倉庫の契約が必要になるでしょう。
賃料や保管管理のコストの増加にもつながるため、経営視点でもこの課題は無視できません。
2-4.セキュリティを担保できない
紙の図面は、鍵付きで保管しても「誰がいつ見たか」を把握しづらく、不正な持ち出しや盗難、無断コピー・撮影などのリスクがあります。閲覧権限の細かな制御や操作履歴の記録が難しく、退職者・外注先経由の漏えいも起こりえます。
さらに、印刷物の置き忘れから、情報が流出するおそれも否定できません。
2-5.管理しづらい
紙管理では、どれが最新版かの見極めが難しく、改訂情報が現場や調達先まで行き渡らないことがあります。複製が増えるほど最新バージョンが分からなくなり、誤配布も起こりかねません。
さらに、誰がどの図面を見ているか把握しづらく、部門間の共有にも手間がかかります。
3. 紙図面の保管で劣化を防ぐ3つのポイント

紙図面を長持ちさせるには、適切な保管環境を整え、収納用品を活用することが重要です。
ここでは、紙図面の保管ポイントを3つ紹介します。
- 温度・湿度を適切に保つ
- 遮光する
- 収納箱を活用する
ぜひ参考にしてみてください。
3-1.温度・湿度を適切に保つ
紙図面は温湿度の変動に敏感です。湿り気が強いと紙がふやけて平面性が落ち、乾きすぎると繊維が締まり、折れや割れの原因になります。湿度は40〜60%を目安に、急な温度変化は避けましょう。
温湿度計で常時確認し、空調・除湿・加湿を組み合わせて管理してください。
3-2.遮光する
紙図面は光、とくに紫外線でインクやトナーが退色しやすく、紙自体も黄変します。直射日光の当たらない暗所で保管し、窓際は避けましょう。オフィス照明でも、長時間の曝露により劣化が進むため、UVカットフィルムや遮光カーテン、図面キャビネット用のカバーによる対策がおすすめです。
保管庫から持ち出した場合は、期間を区切って速やかに回収し、保管中は中性紙のインナーフォルダーや封筒で外光を遮ると効果的です。
3-3.収納箱を活用する
図面の形状と頻度に合わせて収納用品の使い分けがおすすめです。頻繁に取り出すものはフラットファイルや図面キャビネットで平置きします。一方、長期保管する図面は、中性紙製の保存箱やPP・PE素材のクリアホルダーを活用しましょう。その際、可塑剤移行の懸念があるPVCは避けてください。
巻き保管は図面保管筒を用い、内径にゆとりを持たせて端部の潰れを防止します。輪ゴムで締め付けず紙ベルト等を使用し、図番・版数・保管期限をラベリングして、取り違えを防ぎます。
重要図面は耐火・防水性のキャビネットを用い、床から離して設置することが重要です。乾燥剤は定期交換し、詰め込みすぎず、通気の確保が長期保存のポイントです。
4.紙図面を効率的に保管する4つの方法

紙図面を無理なく整理・保管するために、次の4つの基本から整えることをおすすめします。
- 案件ごとに分類する
- ラベル(背表紙)のルールを明確化する
- 目録を用意する
- 図面以外の関連資料も一緒に保管する
なお、図面管理を効率的に行うためのポイントをより詳しく知りたい方は、こちらの記事も参考にしてください。
4-1.案件ごとに分類する
案件単位で図面を束ねると迷いません。受注番号・製番・顧客名を共通キーにし、進行中と完了で区分します。さらに、関連書類である仕様書や検査記録も同梱し、色分けラベルで識別しやすくなります。
その結果、検索時間が短くなり、引き継ぎもスムーズにできるでしょう。
4-2.ラベル(背表紙)のルールを明確化する
背表紙ラベルは項目と並び順を統一します。基本は「案件コード-図番-版-保管期限」で、日付は「YYYY/MM/DD表記」です。文字サイズや色分けも決め、貼る位置は背の上端から一定の高さにそろえます。
バーコードやQRコードの採用有無も事前に定めておきましょう。
4-3.目録を用意する
目録は共通様式で作成し、Excelなどで一覧化します。おもな項目は、以下のとおりです。
- 案件コード
- 図番
- 版
- 図面名
- 保管場所番地(棚・段・箱ID)
- 保管期限
- 貸出状況
- 改訂日
また、更新担当と更新日を明記し、改訂や移送のたびに反映しましょう。
ファイルの背表紙にQRコードを付与しておくと、その場で読み取るだけでExcelなどの目録の該当行をすぐに表示できます。これにより、目録と現物のファイルを突き合わせて確認したり、貸出・返却の状況を更新したりする作業が効率化されます。
さらに、保管期限や改訂履歴などの関連情報もファイルを開かずに参照可能です。
4-4.図面以外の関連資料も一緒に保管する
案件ごとのフォルダに図面と一緒に「仕様書・変更指示・検査記録・承認書・見積書・手配書」など関連資料を一式で綴じます。仕切りタブで区分し、表紙に目次と不足チェック欄を設けるとより管理しやすいでしょう。
不足チェック欄は、ファイルに含まれるべき資料の有無を一目で確認するためのリストです。貸出や別管理がある場合は、その理由を記録することで、紛失や漏れを防げます。
さらに、各資料に案件コードと版を記載しておけば、改訂時の差し替えや履歴管理もスムーズに行え、誤用リスクを減らすことにつながります。
なお、金属クリップはばらけやすいため避け、クリアポケットの使用がおすすめです。
5. 紙図面の保管と図面管理システムを併用する4つのメリット

紙は現場で扱いやすい一方、検索性や版管理、共有、セキュリティには限界があります。図面管理システムを組み合わせることで、紙のよさを残しつつ弱点を補えます。ここでは以下4つのメリットをまとめました。
- 必要な図面を素早く探せる
- 最新図面やバージョンを管理できる
- 複数人で共有できる
- セキュリティを保てる
それぞれ見ていきましょう。
5-1.必要な図面を素早く探せる
システムを併用すると、図番・案件コード・キーワードで瞬時に検索可能です。さらに、版や担当者などの属性で絞り込めます。紙図面でも、背表紙のQRコードやバーコードと棚番地を紐づけることで、所在をすぐに特定できるでしょう。
また、手書き注記もOCRで文字を読み取ることで、検索対象に含められます。
5-2.最新図面やバージョンを管理できる
図面管理システムは版管理により常に最新版を表示し、改訂履歴を自動保存できます。また、差分表示で変更点を把握し、承認ワークフローと連動して公開時期も制御可能です。
さらに、変更通知やアクセス権設定により、旧版の誤使用を未然に防げます。
5-3.複数人で共有できる
拠点や部門をまたいだ同時閲覧・共有にも対応しています。また、権限に応じてURL共有や期限付きリンクを設定することで、外部先とも安全に連携可能です。
さらに、更新通知やコメント機能で伝達漏れを防ぎ、チェックアウト機能で上書き競合も避けられます。
5-4.セキュリティを保てる
ユーザーごとのアクセス権や二要素認証、IP制限で不正閲覧を抑止できます。また、操作ログや期限付きリンク、透かし表示で持ち出しを管理する機能を搭載しているシステムもあります。
加えて、暗号化と自動バックアップにより、漏洩の心配が軽減されるでしょう。
6. 図面管理システムを一新してデジタル化が整備された事例|株式会社ニッシン
サーバーの老朽化により、図面を内製で管理することが限界となり、半年の猶予で刷新を決断しました。7回にわたるヒアリングと評価期間により、価格と現場適合に優れたNAZCA5 EDMを採用しました。2023年3月より、新サーバーで稼働しています。
約100名が違和感なく利用開始し、API/AD連携でユーザー管理やシステム連携の基盤も整備。承認フローの全面オンライン化など、デジタル化の拡張に弾みがつきました。
| 導入前の課題 | サーバー老朽化で内製システムが不安定になり、停止リスクが高い |
|---|---|
| 新OS対応・サーバー移行が困難だった | |
| 多くのユーザーが部門をまたいで使うため、それぞれの条件に合った製品が選定できなかった | |
| 実施したこと | 低価格と製造業向け機能に特化したNAZCA5 EDMを選定した |
| 現場の業務フローや要望をヒアリングし、評価版で詳細な要件を詰めた | |
| 必要な機能に絞り細かくカスタマイズを実施した | |
| 得られた成果 | 日常業務に支障なく、約100名の社員が新システムを利用開始 |
| 想定の約半額で刷新し、コストパフォーマンスを大幅改善 | |
| 図面承認フロー完全オンライン化により、DX推進の基盤を整備 |
7.紙図面の保管は図面管理システムとの併用がおすすめ
紙図面は適切な条件のもと保管することが大切です。案件分類・ラベル・目録など、まずは土台を整えましょう。
また、図面管理システムを併用すれば、探索性・版管理の正確性・共有性・セキュリティを着実に向上できます。段階的にデジタル基盤を整えると、コストも抑えやすいです。
「NAZCA5 EDM(ナスカ・ファイブ・イーディエム)」は大手製造業の子会社が開発した現場の声を反映した図面管理システムです。限られた予算で図面管理を効率化したい方は、こちらからお問い合わせください。
参考|NAZCA5 EDM 公式サイト